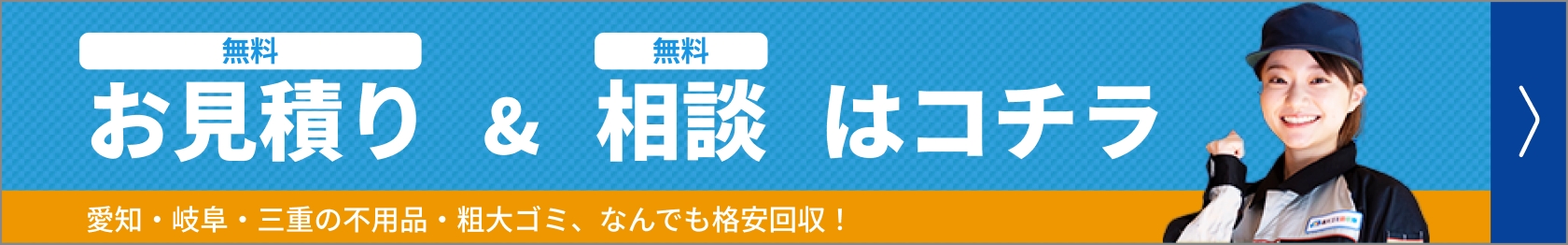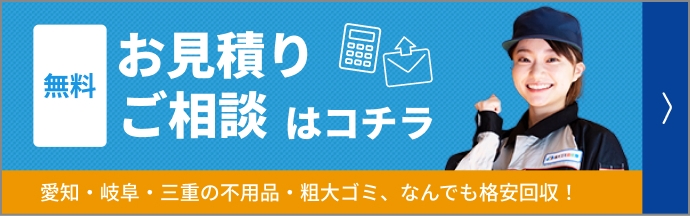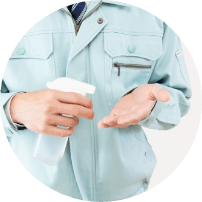空き家の解体費用相場と補助金制度|相続しても老朽化するとトラブルの火種!
この記事は約5分で読めます。
住む予定のない空き家の解体費用相場と、補助金制度について解説します。
空き家の解体工事にかかる費用は、38坪の一軒家では114万~304万円です。しかし、さまざま条件によって変動するため、正確な費用を知るために、出張見積もりを依頼しましょう。
老朽化した空き家は防災や衛生のリスクだけでなく、税金や資産価値に影響を与えます。解体に対するメリット・デメリットも説明しているので、ぜひ参考にしてください。
目次
空き家の解体費用相場と補助金制度

空き家の解体費用は、さまざまな条件によって変動します。ここでは、解体工事の費用相場と、自治体の解体工事を支援する補助金制度について解説します。
解体工事の費用相場
空き家の解体工事にかかる費用は、構造や立地、工事内容によって大きく異なります。一軒家を解体する費用相場と特徴は、以下のとおりです。坪数は、総務省が発表した一軒家の平均坪数38坪で算出しています。
| 構造 | 木造 | 鉄骨造 | RC造 (鉄筋コンクリート造) |
| 解体費用相場 | 114万~190万円 | 152万~228万円 | 228万~304万円 |
| 解体のしやすさ | 比較的に容易 | やや困難 | 困難 |
| 廃材処分の難度 | 木材中心 | 鉄材の分別 | 鉄材・コンクリートの処理 |
| 処分費が占める割合 | 30~40% | 40~50% | 50~60% |
| 振動・騒音の発生 | 低~中 | 中~高 | 高 |
解体工事を検討する際は、構造や立地条件を踏まえて見積もりを取ることが、適正な費用を把握するためのポイントです。解体工事では、構造が頑丈になるほど、騒音や振動の発生が大きくなるため、近隣への対応にかかる費用も増加します。
また、道路幅が狭く重機搬入が難しい場合や、アスベスト含有建材が使用された建物は追加費用が発生するため、現場での出張見積もりを依頼することが重要です。
「粗大ゴミ回収隊」では、ご相談や出張見積もりを無料で承っています。キャンセル料もいただきませんので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
活用できる補助金制度
多くの自治体では、空き家の放置による防災や景観、衛生面の問題を防ぐため、解体に対する補助金制度を設けています。各自治体の補助金制度は、以下のとおりです。
| 都市名 | 補助金の名称 | 補助される費用 |
| 愛知県常滑市 | 危険空家住宅の除却費補助 | 解体費用の4/5 (上限30万円) |
| 岐阜県高山市 | 不良空き家除却補助金 | 解体費用の1/2 (上限50万円) |
| 三重県鳥羽市 | 木造住宅空家除却(解体)工事費補助 | 解体費用の23% (上限20.7万円) |
空き家の補助金制度を申請するためには、必要書類の提出や現地調査など、手続きに時間がかかるため、早めの準備が求められます。さらに、補助金は予算枠が限られているため、工事計画と並行して準備を進めましょう。
空き家を解体するメリット&デメリット

解体を検討する際には、費用だけでなく、将来の土地活用や地域環境への影響など、長期的な視点で考える必要があります。ここでは、空き家を解体するメリットとデメリットについて、詳しく説明します。
メリット:リスクを断ち、土地を活かせる
空き家を解体するメリットは、以下のとおりです。
- 管理責任から解放される
- 近隣トラブルを避けられる
- 犯罪トラブルを防げる
- 土地を活用しやすい
空き家の所有者は建物の管理責任があり、定期的な修繕や清掃を行う義務が発生し、思った以上に時間と費用必要です。もし、建物や敷地の管理不備によって、他人に損害を与えた場合、所有者は賠償責任を負う可能性があります。
また、老朽化が進んだ建物は、倒壊や火災の危険性、害虫や害獣の温床になることがあり、周囲の生活環境にも悪影響を与えます。さらに、放火や不審者侵入などのトラブルを招く可能性も放置できません。
空き家を解体することで、管理責任から解放され、近隣トラブルや犯罪被害などを防ぐ効果が期待できます。さらに、建物を撤去して更地にすると、売却や駐車場運用など土地の活用がしやすい点も大きなメリットです。
不用な空き家は解体によって、将来的な損失を防ぎ、資産価値を高めやすくなります。
デメリット:費用と負担が増える可能性がある
空き家を解体するデメリットには、以下があります。
- まとまった費用がかかる
- 税額が上がる可能性がある
- 心理的な負担がある
空き家の解体は、規模や構造によっては数百万円単位のまとまった費用が必要です。特に、鉄骨造やRC造などは工期も長くなりやすく、重機や専門技術が求められるため、木造よりも高額になる傾向があります。
さらに、建物を取り壊すと、土地にかかる固定資産税の優遇措置である住宅用地の特例が適用されなくなる場合があります。住宅用地の特例とは、住宅が建っている土地について税金を軽減する制度で、建物を解体して更地にすると、翌年度から土地の固定資産税が数倍に増えることがあるため、解体しない理由になることもあります。
また、長年家族が暮らした思い出の詰まった建物を壊すことには、大きな心理的負担を感じる方も少なくありません。費用面や税制面、精神面での負担を総合的に考慮し、解体の必要性や時期を見極めることが重要です。
空き家の解体工事に関する手続き

空き家の解体工事は、ただ重機を入れて壊すだけでは終わりません。中でも、解体に関する手続きに不備があると、工事が止まってしまう恐れがあります。ここでは、空き家の解体工事に関する重要な手続きについて詳しく解説します。
空き家の解体工事に関する手続きの流れについては、こちらの記事をご覧ください。
補助金制度の申請手続き
空き家解体の費用負担を軽減するために、多くの自治体では補助金制度を用意しています。申請は解体工事を行う前に手続きを進める必要があり、工事を始めると対象外になるため、補助金の交付決定後でないと着工できません。
補助金制度の申請手続きに必要な書類は、以下のとおりです。
- 申請書
- 見積書
- 建物の登記簿謄本
- 現況写真 など
自治体によっては、現地確認や不良空家判定が必要な場合があり、審査期間は数週間から1か月程度かかるため、スケジュールに余裕を持つことが大切です。
補助金額は自治体や条件によって異なりますが、工事費用の一部が支給されるため、実質的な負担を大きく減らせます。
建物滅失登記の提出
解体工事が完了したら、登記簿上から建物を削除するため、法務局に建物滅失登記を提出しましょう。提出期限は工事完了から1か月以内と定められており、遅れると過料が発生する可能性があるため、注意が必要です。
申請に必要な書類には、以下があります。
- 建物滅失登記申請書
- 建物滅失証明書
- 解体業者の資格証明書
- 解体した建物の地図や写真 など
建物滅失登記の提出を怠ると、現況と登記情報が一致せず、土地売却や新築建築の際に手続きが滞る原因になります。
また、固定資産税の軽減措置が受けられない可能性もあるため、手続きは確実に行いましょう。解体業者が登記まで代行してくれる場合もありますが、費用や対応範囲を確認しておくと安心です。
登録有形文化財の解体手続き
空き家が古民家などの価値のある建物の場合、登録有形文化財として登録されている場合があります。登録有形文化財に指定されている建物は、通常の解体工事とは異なり、文化庁や自治体の教育委員会への届出や許可申請が必要です。
許可なく解体すると、文化財保護法違反となり、罰則が科される可能性があります。申請に必要な書類は、以下のとおりです。
- 解体理由書
- 設計図面
- 構造や歴史的価値に関する資料
- 現況写真 など
場合によっては、解体前に記録保存のための測量や写真撮影が求められ、解体の許可が出るまでに数か月かかることもあり、解体スケジュールに大きな影響を及ぼします。
古民家などの解体では、文化財指定の有無を早期に確認し、専門知識を持つ業者や行政機関と連携して手続きを進めることが重要です。
相続しても老朽化するとトラブルの火種!

相続によって取得した建物が老朽化すると、さまざまなトラブルの火種になる可能性があります。放置による問題は時間の経過とともに深刻化するため、早めの判断と対策を行いましょう。
固定資産税が増額される
老朽化した空き家をそのまま放置すると、固定資産税の負担が増える場合があるため、注意が必要です。空き家が老朽化によって、倒壊や崩壊の恐れや著しく衛生上有害であると判断した場合、行政から改善勧告や命令が出されます。
改善がされない場合、行政が特定空き家として指定すると、土地の固定資産税に適用されていた住宅用地の特例が外れてしまい、税額が最大6倍に跳ね上がります。勧告や命令を無視すると、行政代執行により強制的に解体されるリスクもあるため、固定資産税の優遇を維持するためにも、早めの修繕や解体などの対策を行いましょう。
資産価値が大きく下がる
建物は時間とともに劣化し、古くなるほど市場での評価は下がります。外観や安全性の問題から買い手がつきにくくなり、不動産としての価値が著しく下がり、売却は困難です。
特に、老朽化の進んだ建物は、土地としての価値しか見られないことも多く、解体費用込みでの売却価格しか提示されないこともあります。売却しづらくなると、維持費や固定資産税だけがかかり続けるため、老朽化が進む前に活用方法を検討し、必要であれば解体して更地にする選択が有効です。
近隣トラブルが発生する
老朽化した空き家は、景観の問題だけでなく、近隣への安全や衛生面の影響も大きくなります。空き家を放置し続けることで、屋根や外壁の一部が剥がれて飛散したり、庭の雑草や樹木が隣地に越境したりすることは珍しくありません。
さらに、放置された建物は害虫や野生動物の住みかとなり、悪臭や騒音を引き起こす場合もあります。近隣への被害が続くと、最悪の場合は近隣住民から損害賠償を求められる可能性があります。
「知らなかった」「遠方だから」は通用せず、空き家の放置は法的リスクを伴います。近隣との関係を守るためには、適切に管理を続けるか、早期の解体によるリスク排除が不可欠です。
空き家の解体に関するよくある疑問

解体工事に関するよくある疑問について、分かりやすく解説します。
家財が残ったままでも解体できる?
家財が残ったままでは解体工事が進められないため、費用が割増になる場合があります。家財や不用品などの分別や、搬出作業が増えるため、工期の延長も避けられません。解体費用を抑えるために、家財は自分で片付けるか、不用品回収業者に依頼しましょう。
また、貴重品や相続の対象品が混在している場合、誤って捨ててしまわないよう、注意が必要です。遺品整理で捨ててはいけないものについて、こちらの記事で解説しています。
解体にかかる期間はどれくらい?
空き家の解体にかかる期間は、建物の構造や規模、現地の状況によって異なりますが、平屋か2階建ての木造住宅であれば5~10日程度です。軽量鉄骨造の場合は基礎撤去に時間がかかるため、7〜14日程度見ておきましょう。
RC造(鉄筋コンクリート)の建物は重機が必要なため、10〜20日以上かかります。
見積もり・許可取得などの準備期間を含めると1カ月以上かかる場合もあるため、解体は時間に余裕を持って進めましょう。
工事期間が伸びることはある?
作業効率の低下や予期せぬトラブルによって、工事期間が伸びることがあります。工事期間が伸びる原因は、以下のとおりです。
- 天候不良による休工
- 地中埋設物の発見
- アスベストの処理
- 近隣トラブルによる中断
- 行政手続きの遅延 など
予想以上の基礎や配管が発見された場合は、追加の撤去作業によって日数が増える場合や、撤去物の分別や廃棄ルールが厳しい地域では、処理に時間を要することもあります。
建物にアスベスト含有建材が使用されている場合は、適切な処理が求められるため、通常の解体工事よりも工事期間が長くなります。工期が伸びるリスクを最小限に抑えるために、事前の調査や業者との密な連絡が重要です。
1950~1990年代に建てられた建物は、アスベストが使われている可能性があるため、解体前に調査をおすすめします。こちらの記事で、アスベストがある建物に関する疑問について解説しているので、参考にしてください。
空き家の解体は粗大ゴミ回収隊にお任せください

住む予定のない空き家の解体は「粗大ゴミ回収隊」にお任せください。建物に残された家財の回収から家屋の解体、がれき類の処分まで、すべて対応します。丸ごと自社で実施できるため、重複する費用がまとめられ、複数社に依頼するよりもお得です。
遺品整理が伴う場合でも、遺品整理士の資格を持ったスタッフが、まごころを込めて丁寧に作業を進めます。残された仏壇や神棚の魂抜き、お焚き上げなど、適切な対応が可能です。
急な片付けや大型ゴミの処分にもスピーディーに対応します。ぜひ、お気軽にご相談ください。
困ったときは無料相談がおすすめ
記事を読んでいて「結局どうしたらいいかわからない」「すぐになんとかしたい」「直接専門家に相談してみたい」という方も多いはず。そんなときは無料相談窓口を利用してみましょう!専門のオペレーターが対応いたします。


不用品回収・ゴミ屋敷の清掃などなんでもお任せください!
業界最安値の料金プラン9,800円~
相談・出張お見積り
完全無料!
365日24時間対応ですので、どうぞお気軽にご相談ください!
軽トラック
積載プラン間取りの目安:1R~1K
9,800円(税込)

1.5tトラック
積載プラン間取りの目安:1K~1LDK
39,800円(税込)

2tトラック
積載プラン間取りの目安:1LDK~2LDK
59,800円(税込)
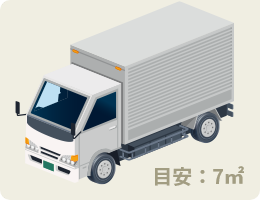
4tトラック
積載プラン間取りの目安:3LDK~戸建て
80,000円(税込)
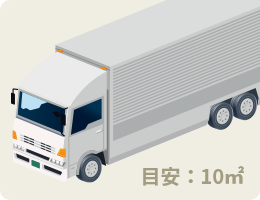
※軽トラック~1.5tトラックなど、間の料金にも柔軟に対応いたしますので、スタッフまでお気軽にお申し付けください。
※スタッフに「引っ越し割引希望」とお伝えください!
※スタッフに「WEB割引希望」とお伝えください!