SDGsとは
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS粗大ゴミ回収隊はSDGsの
実現に貢献します
SDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)とは、2015年9月の国連サミットにおいて、
全会一致で採択された国際目標です。「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現のため、
2030年を年限とする17の国際目標で、その下に、169のターゲット、232の指標が定められています。
SDGsは全ての国が取組むべき課題であること、また、あらゆるステークホルダーがめざすべき目標とされています。

粗大ゴミ回収隊の取り組み
粗大ゴミ回収隊では、国連が提唱するSDGs(持続可能な開発目標)に賛同し、
地域社会の発展と地域に住まう人々の安全で豊かな暮らしの実現のため
SDGsの達成に向けた取組に真摯に向き合ってまいります。

GOAL.10 人や国の不平等をなくそう

雇用均等化の取り組み
女性スタッフの雇用促進
- 採用基準の見直し:性別に関係なく、候補者の能力や経験を重視した採用基準を設定。
- フレキシブルな勤務形態:子育てや介護のための柔軟な勤務時間や在宅勤務を導入。
- リーダーシッププログラム:女性がキャリアアップできるよう支援するリーダーシップ研修やメンタリングを提供。
外国人スタッフの雇用促進
- 勤務時間の調整:宗教的な理由で必要な場合、礼拝の時間に合わせて勤務時間を変更。
- 食事の配慮:宗教上食べられない食品に配慮した食事提供。
- 多言語の求人情報:外国人が応募しやすいよう、多言語で求人情報を提供。
- 文化理解の促進:異文化理解を深めるための研修やワークショップを実施し、多様性を尊重する職場文化を育む。
- ビザサポート:外国人スタッフのビザや労働許可の取得を支援。
障がい者の雇用促進
- 障がい者対応の職場環境:バリアフリーな職場の整備と必要な補助器具を提供。
- 特別支援プログラム:障がい者向けの職業訓練や適応支援プログラムを提供。
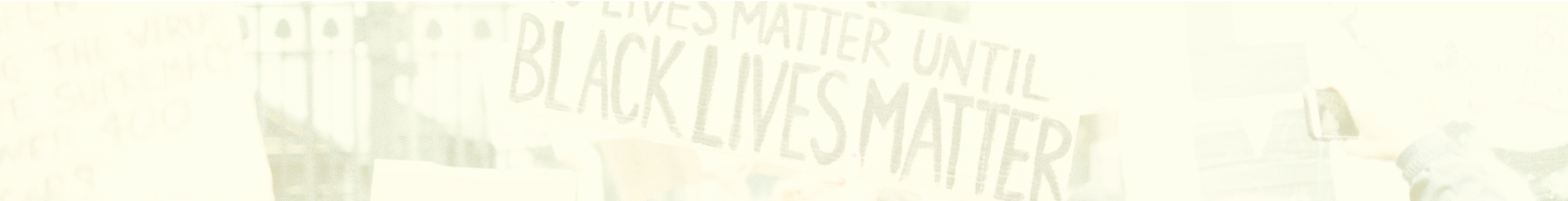
差別防止のための取り組み
アンチハラスメントポリシー
- ポリシーの制定と周知:職場内のハラスメントや差別を無くすための明確な規定を作成し、全社員に徹底的に周知する。
- 通報制度の設置:ハラスメントや差別が報告された際に、迅速かつ公正に対応するためのシステムを整備。
教育とトレーニング
- ダイバーシティ・トレーニング:多様性を尊重し、差別を防ぐために、全社員が定期的に受ける研修を実施。
- インクルージョン・ワークショップ:異なる背景を持つ人々が公平に働けるよ うに、インクルージョンを促進するワークショップを開催。
公正な賃金制度
- 給与の透明性の確保:職種や役職ごとに公正な賃金を設定し、その体系を透明にする。
- ジェンダーギャップの解消:性別を問わず、同一労働同一賃金を実現する。

GOAL.11 住み続けられるまちづくりを
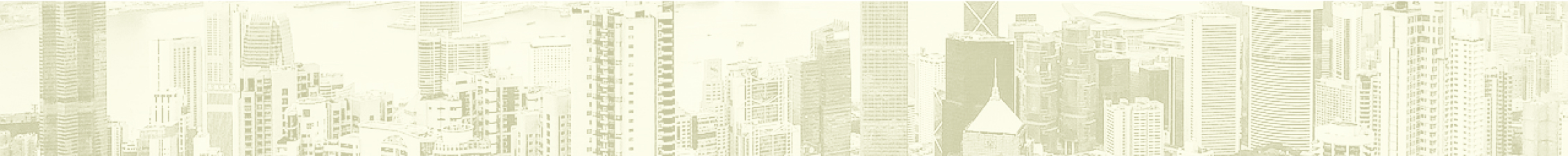
環境改善の取り組み
低公害車両の普及
- 低公害車両の導入奨励:電気自動車やハイブリッド車の普及を促す政策を推進。
- 公共交通の充実:公共交通機関の利用を促進し、インフラを改善して自家用車の使用を減らす。
廃棄物管理の向上
- リサイクルプログラムの導入:家庭や企業がリサイクルを行いやすくするための分別収集システムを設ける。
- コンポスト化の推進:生ゴミをコンポスト化し、堆肥として再利用するプログラムを開始。
都市緑化の促進
- 緑地の増設:都市部に公園や緑地を新設し、空気を浄化し市民の健康を促進。
- 屋上緑化の推進:建物の屋上に緑を増やすことで、都市のヒートアイランド現象を軽渲する。

災害リスク軽減の取り組み
災害リスク軽減計画の策定
- 粗大ゴミに関するリスクの分析:災害時に粗大ゴミが多く存在することで生じるリスクを詳細に分析し、その情報を地域に周知する。
防災計画の整備
- 地方自治体との連携:地方自治体やコミュニティと協力して防災計画を作成し、これを定期的に更新し、災害への対応力を高める。

GOAL.12 つくる責任 つかう責任

有害化学物質の適切な管理
有害物質の規制強化
- 規制と安全な代替品への転換:有害化学物質の使用を制限し、安全な代替品の使用を促進するための政策を実施。
企業の監査
- 化学物質管理の監査:企業が使用する化学物質の管理を定期的に監査し、法令遵守を確認する。
廃棄物の適正処理
- 有害廃棄物の専用処理施設:有害廃棄物を安全に処理するための専門施設を整備し、適切な処理を実施。
- 廃棄物削減プログラム:製造業等での廃棄物を削減し、リサイクルや再利用を促進するプログラムを実施。
環境汚染防止
- 環境モニタリングの強化:空気、水、土壌の環境を定期的にモニタリングし、汚染状況を継続的に監視。
- 汚染防止技術の導入:産業施設に汚染防止技術を導入し、排出物の浄化を進める。

リサイクルプログラムの強化
分別回只の徹底
- 家庭と企業への分別指導:家庭や企業がリサイクル可能な資源を正確に分別して回収する体制を徹底する。
リサイクルセンターの設置
- 地域リサイクルセンターの設立:リサイクル率を向上させるために、地域ごとにリサイクルセンターを設置。
再利用の促進
- リユースショップの運営:中古品や不要品を扱うリユースショップを開設し、消費者に再利用のメリットを啓発。
- リフィルステーションの導入:日用品のリフィルステーションを設け、使い捨て容器の使用を減らすことを促す。

GOAL.15 陸の豊かさも守ろう

再利用促進プログラム
木材製品の再利用
- 回収した木材の再活用:回収した木材製品を修理・再利用し、廃棄される木材の量を削減。再利用可能な家具はリサイクルショップで販売する。
- 木材パレットのリサイクル:企業から回収した木材パレットをリサイクルし、新たなパレット製造に活用。
璭境教育と啓発活動
- 森林保護キャンペーン:森林保護の重要性を広く伝えるキャンペーンを実施し、持続可能な森林管理の大切さを地域住民や顧客に教育。
- 植樹活動の支援:売上の一部を植樹活動に寄付し、森林再生を促進。
環境に優しいサービス
- エコフレンドリーな収集車両の導入:排出ガスが少ない車両や電動車を使用し、不用品回収時の環境負荷を減らす。
- 循環型経済の推進:回収した不用品を資源として再利用し、循環型経済を推進。廃棄物の資源化を進める。

GOAL.17 パートナーシップで目標を達成しよう

地域社会との連携強化
地元自治体との協力
- 不用品回収とリサイクルの共同実施:地域の自治体と連携して、効率的な不用品回収とリサイクルプログラムを展開。地域住民と共に回収イベントを開催。
- NPOとのパートナーシップ:環境保護活動を行うNPOと連携し、回収した不用品の適切な処理と再利用を促進。
企業との協力
- 廃棄物管理の共同プロジェクト:他企業と共同で廃棄物管理の効率を向上させるプロジェクトを実施。例えば、共同でリサイクル施設を運営。
- サプライチェーンの持続可能性:サプライチェーン全体で持続可能な廃棄物管理を推進し、供給業者やパートナー企業と共に持続可能性を高める取り組みを進める。
国際的なパートナーシップ
- グローバルリサイクルネットワークへの参加:国際的なリサイクルネットワークに加わり、技術や知識の共有を通じてグローバルな廃棄物管理を改善。
- 技術支援と知識交流:海外のリサイクル業者や環境保護団体との技術支援や知識交流を行い、国際的な廃棄物管理能力の向上を目指す。






